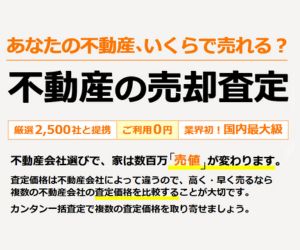不動産売却時の「印紙税」はいくらかかる?売買契約書や重要事項説明書にかかる税金の「節約術」とは
配信日: 2025.06.23

当記事では、不動産売却時の印紙税について、仕組みから具体的な税額、負担を抑える方法までをわかりやすく解説します。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
不動産売却にかかる「印紙税」とは?
印紙税とは、経済的な取引に伴って作成される特定の文書に課される税金です。
不動産の売買契約書は、印紙税法で定められた「課税文書」に該当するため、印紙税がかかります。
一方、重要事項説明書は、宅地建物取引業法に基づいて作成・交付される文書であり、原則として印紙税の課税対象となる文書には該当しません。そのため、重要事項説明書に印紙を貼る必要はありません。
契約書に適切な金額の収入印紙を貼り付け、消印することで納税が完了となります。
いくらかかる? 不動産売買契約書の印紙税額
不動産売買契約書にかかる印紙税額は、契約書に記載された不動産の売買金額によって定められています。
具体的な税額は表1のとおりです。
表1
| 契約金額(記載金額) | 税額(本則) | 税額(軽減措置適用後) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
※国税庁「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」を参考に筆者作成
上記の表を見るとわかるように、売買金額が高くなるにつれて印紙税額も上がりますが、軽減措置が適用されることで税負担は抑えられています。
不動産を高く売るなら
無料でプラン請求! 公式サイトを見る
印紙税を節約する方法
不動産売却にかかる印紙税は、いくつかの方法で負担を軽減できる可能性があります。次に紹介する2つの節約術を参考にしてください。
契約書は1通だけ作成する
不動産売買契約書は、売主用と買主用の2通を作成し、それぞれに印紙を貼付して保管するのが原則となりますが、取引によっては、原本1通とコピーを保管するという方法が可能になります。
印紙税の貼付を原本の1通にすれば、印紙税の負担を半分に抑えることができます。
ただし、買主が原本での保管を希望する場合や金融機関のローン手続きで原本が必要となる場合など、状況によっては1通での対応が難しいケースもあるため、相手方の合意の上で進めましょう。
電子契約を活用する
書面ではなくデータで契約を締結した場合、印紙税法上の「課税文書」には該当しないという解釈になり、印紙税の課税対象外となります。電子契約とは、インターネット上のデータとして契約書を作成し、締結する方法です。
しかし、電子契約を利用するには、売主・買主双方と不動産業者が電子契約に対応している必要があります。
また、電子署名サービスを利用するために料金がかかる場合もあるため、費用面を比較検討する必要があるでしょう。
印紙税の仕組みを理解して節約術を見つけよう
不動産売却時の印紙税は、売買契約書にかかる税金で、契約金額に応じて税額が決まります。重要事項説明書には原則として印紙税はかかりません。
印紙税は契約書の作成方法を工夫したり電子契約を利用したりすることで、負担を軽減できる可能性があります。印紙税について正しく理解することで、節約できる方法が見つかるでしょう。
出典
国税庁 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
不動産を高く売るなら
無料でプラン請求! 公式サイトを見る