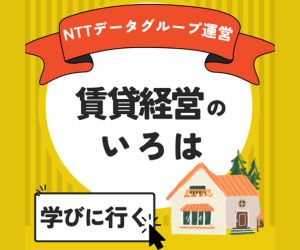相続した土地に「賃貸併用住宅」を建てようと思いますが、住宅ローン減税と家賃収入のバランスはどうなりますか?
配信日: 2025.06.20

しかし「住宅ローン減税は使えるか」「家賃収入にも税金がかかるのか」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
当記事では、賃貸併用住宅を建てる際に知っておきたい、住宅ローン減税と家賃収入に関するポイントをわかりやすく解説します。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
相続した土地を「賃貸併用住宅」にするメリット
賃貸併用住宅は、建物の一部を自身の自宅とし、残りの部分を賃貸に出して家賃収入を得る住宅です。相続した土地を賃貸併用住宅として活用すると、住む場所を確保しながら収入を得られるというメリットがあります。
ただし、建築費用や空室リスク、入居者のトラブル対応、建物の維持管理など、賃貸経営にはお金や手間が発生することも認識しておきましょう。
「住宅ローン減税」の基本
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、マイホームを取得したり増改築したりする際に組んだ住宅ローンについて、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除できる制度です。
税金が軽減されるため、住宅購入を検討している多くの方が利用を考える制度でしょう。賃貸併用住宅の場合でも、いくつかの条件を満たすことで、住宅ローン減税が適用されます。
第一に、建物の床面積のうち、自身が住む部分の床面積が全体の2分の1以上であることが条件です。
また、控除の対象となる借入金の額は、自身が住む部分の床面積に対応する部分のみとなります。
たとえば、建物の総床面積が200平方メートルで、自宅部分が120平方メートル(60%)、賃貸部分が80平方メートル(40%)の場合、住宅ローン減税の対象となる借入金は、住宅ローン全体の60%相当額となります。
得られる家賃収入と発生する税金
賃貸併用住宅の大きな魅力は、毎月家賃収入を得られることです。家賃収入を住宅ローンの返済に充てれば、自身の住居を用意する負担を大きく減らせます。
しかし、家賃収入は「不動産所得」となり所得税と住民税の課税対象です。
家賃収入から必要経費(固定資産税、都市計画税、ローンの利息部分、減価償却費、修繕費、管理委託料など)を差し引いた残りの所得に対し、毎年税金がかかってきます。
土地活用を検討するなら
無料査定実施中! 公式サイトを見る
賃貸併用住宅における住宅ローン減税と家賃収入のバランス
賃貸併用住宅では、住宅ローン減税による節約が期待できますが、家賃収入として得た不動産所得には税金がかかるため、バランスを考慮しなくてはなりません。
家賃収入による所得が増えると、所得税や住民税の税率が高くなる可能性があります。場合によっては、住宅ローン減税で軽減される税金よりも、家賃収入にかかる税金のほうが大きくなるケースも考えられます。
よって、賃貸併用住宅では、以下の要素を総合的にみて、手元に残るお金がプラスになるかを検討する必要があるのです。
・住宅ローン減税でいくら税金が軽減されるか
・家賃収入から経費を差し引いた所得がいくらになるか
・不動産所得に対していくら税金がかかるか
・ローンの返済額はいくらか
賃貸併用住宅の建築実績が豊富なハウスメーカーや、不動産や税金に詳しい税理士などに相談して、より現実的な計画を立ててください。
賃貸併用住宅は減税と収入のバランスで検討しよう
相続した土地を賃貸併用住宅として活用すると、住まいを確保しながら安定収入を得られる点が魅力です。
しかし、検討する際には、住宅ローン減税と家賃収入のバランスを考慮しなくてはなりません。不安がある場合は、専門家に相談し、自身の状況に合ったプランを一緒に考えてもらいましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
土地活用を検討するなら
無料査定実施中! 公式サイトを見る