平均年収「約750万円」! ドラマでおなじみ「科捜研」職員の仕事とは?日本の平均的なサラリーマンよりも「収入」は高いの?
配信日: 2025.06.14
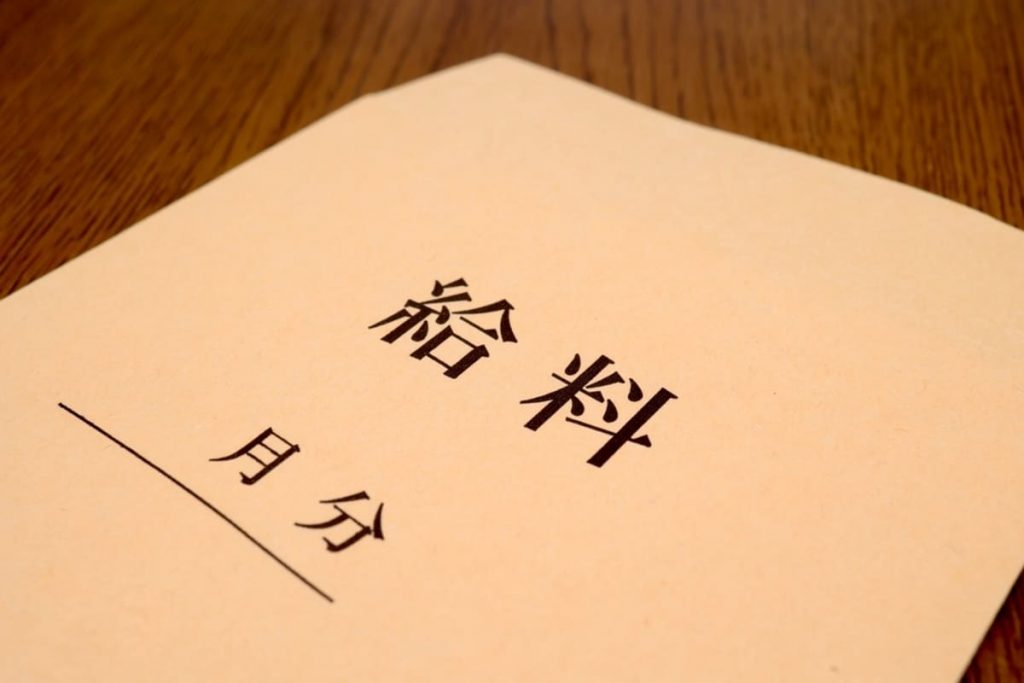
本記事では、科捜研はどのような業務を行い、どのくらいの年収を得ているのかに触れ、日本の平均的なサラリーマンと比較しながら、その実態にせまります。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
目次
「科捜研」職員の仕事とは? 科学捜査の最前線
科捜研で働く職員は、科学捜査研究所鑑定技術職員と称されます。都道府県警察に属する地方公務員ですが、警察官ではなく研究職員で、その役割は多岐にわたります。
科捜研の組織は大きく分けて、表1の通りです。
表1
| 職種 | 業務内容 |
|---|---|
| 化学科 | 火薬や油類の鑑定、覚せい剤や大麻などの違法薬物や毒物の鑑定、微細証拠物の検査など |
| 物理科 | 出火事件などの原因究明、銃器や弾丸などの鑑定、脅迫電話などの音声鑑定、防犯カメラの画像解析など |
| 法医科 | 血液や毛髪などからのDNA型鑑定、白骨死体の復顔など |
| 文書科 | 脅迫文書などの筆跡鑑定、印影や印刷物の鑑定など |
| 心理科 | ポリグラフによる鑑定、犯罪者プロファイリングなど |
※厚生労働省 職業情報提供サイト job tag「科学捜査研究所鑑定技術職員」を基に筆者作成
これらの業務を通じて、科捜研職員は警察の捜査を科学的な根拠に基づいて支援し、事件解決や犯罪の予防に貢献しています。
「科捜研」職員の年収はどのくらい?
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、科捜研職員を含む「研究者」(従業員10人以上の企業に勤める)の「きまって支給する現金給与額」(平均月収)は47万100円、「年間賞与その他特別給与額」は186万3300円です。したがって、研究者の平均年収は750万4500円となります。
ただし、賃金構造基本統計調査の「研究者」には科捜研職員以外にも土木・建築工学研究者や情報工学研究者なども含まれます。科捜研職員に限定した場合の金額とは異なる点にご注意ください。
日本の平均的なサラリーマンとの比較
続いて、日本の平均的なサラリーマンの年収と比較します。
「令和6年賃金構造基本統計調査」では、一般労働者(従業員10人以上の企業に勤める)の「きまって支給する現金給与額」は35万9600円、「年間賞与その他特別給与額」は95万4700円となっています。よって、平均年収は526万9900円です。
科捜研職員の平均年収750万4500円と比較すると、科捜研職員の方が223万4600円高いことになります。
また、科捜研職員は地方公務員であるため、その給与体系は地方公務員法第24条5項により、各都道府県の条例で定められます。安定した収入と昇給が見込める公務員であること、そして専門性の高い職種であることを考慮しても、比較的恵まれた収入を得られる可能性のある職種といえるかもしれません。
科捜研職員を含む「研究者」の平均年収約750万円|平均的な労働者よりも約220万円高い
ドラマの世界では華やかに描かれる科捜研職員ですが、その仕事は科学的知識と地道な努力が求められる専門職です。科学的な捜査に基づいて警察を支援し、事件の解決や犯罪の予防に貢献しています。
科捜研職員を含む「研究者」の平均年収は750万4500円です。一方、日本の平均的な労働者の平均年収は526万9900円となっており、研究者の方が223万4600円高くなっています。
出典
厚生労働省 職業情報提供サイト job tag 科学捜査研究所鑑定技術職員
e-Stat 政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査 / 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号1
e-Stat 政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査 / 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類 表番号1
e-Gov 法令検索 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー























