「全国民一律2万円」の給付金をめぐり“賛否の声”が分かれる理由とは?いま求められている支援のかたちを解説
配信日: 2025.08.05
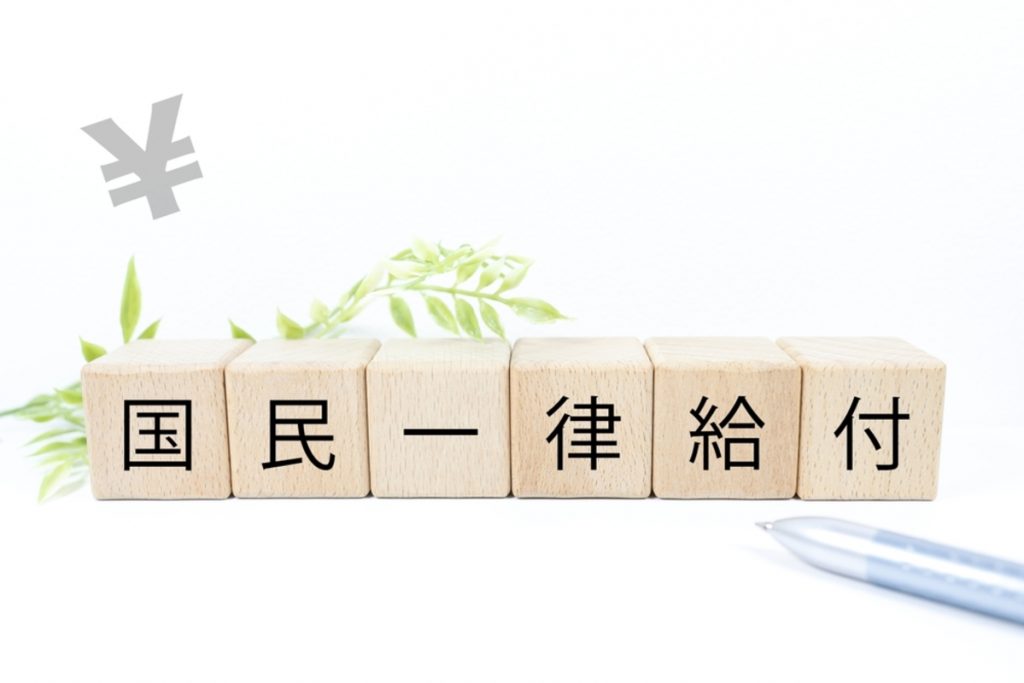

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
給付金をめぐり賛否の声が分かれる理由は? 主な原因と背景を探る
2025年、政府は物価高対策として国民一人あたり2万円を現金給付する政策を打ち出しました。しかし、この給付金には多くの国民から反対の声が上がっており、一般社団法人共同通信社が実施した全国電話世論調査では、賛成41.2%に対して反対は54.9%という結果でした。
反対理由として以下のような意見があるようです。
・「選挙目的のバラマキ」と受け取られていること
・給付金の金額が物価高への根本的対策としては十分と感じられないこと
・特定の層(非課税世帯や子育て世帯など)への上乗せ支給が不公平感につながっていること
・給付実施の背景に「税金の無駄遣い」や「一時しのぎ」といった疑念が残ること
また、一時的な現金給付は持続的な成長には必ずしもつながらないとの指摘も強く、「納得できない」と感じている人も多いのが実情のようです。
給付金の問題点は? 財政負担や効率性の課題
現金給付の最大の課題は、その財源と効率性です。給付金政策は即効性が期待できる一方、数兆円規模もの巨額な公費が必要となります。例えば2025年の2万円給付の場合、総額で3兆円規模と想定されており、財政負担は大きくなることが窺えます。
その一方、給付金の多くが消費ではなく貯蓄に回る現象が過去に確認されており、景気刺激の効果が限定的かもしれません。さらに、繰り返し給付金を配布することで持続的な経済活性化への道筋が見えにくくなり、減税などの恒常的な施策のほうが効果的といった指摘もあります。
事務コストや人手不足も問題視されており、自治体や行政現場では「膨大な作業負担」「事務経費の増大」など、現場のひっ迫した状況が懸念されています。
いま求められている支援のかたちは? 給付金以外の効果的な支援策
こうした反発や課題が指摘されるなかで、国民の「本当に必要な支援」への期待・要望も多様化しています。以下では必要な支援として求められていることの一例をご紹介します。
・消費税や所得税の減税
・用途を限定したエネルギーやガソリン、電気料金の補助
・低所得層や子育て世帯など生活困窮者へのターゲットを絞った支援
・雇用や賃上げ政策による中長期的な所得改善策
特に減税施策については、所得税や消費税を引き下げることで直接的に家計の可処分所得が増えるため、手続きもシンプルで行政コストの削減にもつながります。加えて、エネルギー補助金なども財政負担とのバランスを考えながら、必要な層へ的確に支援する重要性が指摘されています。
こうした「給付金に代わる支援」をいかに設計し、国民全体に持続的かつ公平な形で届けるかは、今後の日本の社会保障・経済政策の大きな課題となるでしょう。
まとめ
現金給付に対する世論の反対や疑問の背景には、「一時的な効果」や「不公平感」「選挙対策」が色濃く映っています。一方で、生活がひっ迫する市民にとっては現金給付は即効性のある救済策であることも事実です。
今後は、安易なバラマキに頼るのではなく「財政の持続可能性」「公平かつきめ細やかな支援」「経済活性化へ直結する中長期的な対策」といった点が重要となります。
国民一人ひとりが税金の役割や支援策の本質を理解し、自分自身や家族の生活にも直結する議論を主体的に見つめていくこと、これが今後の持続的な成長社会に向けた大切な一歩となるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー






















