相続税が「210万円」減る!? 生命保険の「非課税枠」でできる節税対策とは
配信日: 2025.02.27


サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。
早稲田大学卒業後、大手メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超える。その後、保険代理店に勤め、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得。
現在、サマーアロー・コンサルティングの代表、駒沢女子大学特別招聘講師。CFP資格認定者。証券外務員第一種。FPとして種々の相談業務を行うとともに、いくつかのセミナー、講演を行う。
趣味は、映画鑑賞、サッカー、旅行。映画鑑賞のジャンルは何でもありで、最近はアクションもの、推理ものに熱中している。
相続における「生命保険非課税枠」とは何か?
相続税を算出するに当たり、2つの大きな控除があります。
1つは「基礎控除」で、相続財産額から無条件で控除されます。すなわち、基礎控除額の範囲内に相続財産が収まれば、相続税の対象にはなりません。
基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
もう1つの控除は「生命保険の非課税枠」です。これは、被相続人が被保険者となり、相続人が保険金受取人となった場合、その死亡保険金に適用されます。死亡保険金からは「500万円×法定相続人の数」が控除され、それが「生命保険の非課税枠」です。
生命保険の非課税枠は、例えば相続人(実際に保険金等の財産を相続する人。相続放棄をしている人は除く)が「配偶者と子3人」の計4人いる場合は2000万円、相続人が子1人のみの場合には500万円となります。
⽣命保険の死亡保険⾦は、亡くなった⼈が所有していた財産ではありません。しかし、被相続⼈の死亡を理由に⽀払われるので、⽣命保険の死亡保険⾦には、相続と同じ効果があります。それゆえ、死亡保険金は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象になっています。
したがって、被相続人を被保険者にした生命保険を付保すれば、基礎控除に加え、生命保険の非課税枠も使用することが可能になります。この仕組みを使って節税を考えるのが、生命保険の非課税枠を利用した節税法です。
節税対策の仕組みと、保険の設定の仕方
節税対策を行う場合、保険を次のように設定する必要があります。
1. 保険の種類:毎年(あるいは毎月)払いまたは一時払い終身保険
2. 保険契約の設定:
契約者=保険料支払者:被相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人(単独でも複数でも可)
なぜこのような保険の種類と契約の設定が必要なのか、以下に説明します。
1. 終身保険であるべき理由
いつ死亡しても保険金が支払われるようにするためです。
2. 被相続人が持っている現金で、保険料を支払う理由
被相続人が持っている現金はいずれ相続財産になるので、相続税説明のためには相続財産を少しでも減らす必要があります。被相続人が保険料を支払うことで、相続財産を減らす効果があります。
3. 保険契約の設定
契約者(保険料支払者)・被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人にすると、死亡保険金が相続税の対象になり、生命保険の非課税枠も適用されます。すなわち、遺産を現金ではなく「生命保険の非課税枠が付いた死亡保険金」の形で相続人に渡すことができ、生命保険の非課税枠の部分に相当する相続税が節税できます。
これが、生命保険を使った相続税の節税方法です。
4. 保険料の支払い方法
理想的な支払い方法は毎年(月)払いですが、そのためには健康診査に通りやすい若い頃から相続を考え、保険に加入しておく必要があります。それができなかった場合の対策として、一時払い終身保険があるのです。
一時払いの終身保険は、生命保険加入に当たり健康診査がそれほど厳しくないので、高齢になってからでも加入することができます。その代わり保険料は高く、保険料が保険金と同等になることもありますが、そうなっても生命保険非課税枠相当分が課税されないので、節税効果があります。
どのくらい節税が可能になるか?
それでは、生命保険を活用した場合の節税額がいくらになるか、一時払い終身保険を使った場合で確認してみましょう。前提条件は次のとおりです。
● 被保険者および長男、次男、長女の4人家族(法定相続人は長男、次男、長女の3人
● Aは生命保険を節税対策として使わない場合、Bは生命保険を使った場合とする
● 一時払い終身保険の保険料は1500万円、死亡保険金を1500万円とする
下表1も参照してください。
表1 相続税総額の計算と節税額
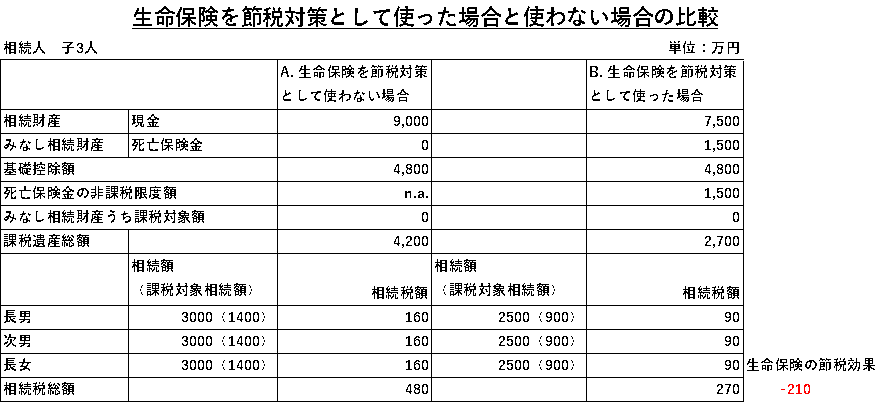
筆者作成
まず相続財産は、Aの場合で9000万円あり、基礎控除の4800万円を引いて、課税遺産総額は4200万円になります。
これに対しBは、一時払い終身保険料として1500万円を使うので、相続財産は7500万円になります。みなし相続財産(死亡保険金)が1500万円になりますが、生命保険の非課税枠を使えるので、500万円×3人=1500万円が非課税になります。
その結果、みなし相続財産はゼロになり、基礎控除を引いた課税遺産総額は2700万円となり、BはAと比べて課税遺産総額が1500万円少なくなります。
ここで、長男、次男、長女の3人を合わせて、1500万円相当の相続税を節税できたことになります。
では、実際の相続税はいくらになるでしょうか?
A.生命保険を使わない場合:
法定相続人1人当たりの課税遺産総額:1400万円
1人当たり相続税額:1400万円×15%―50万円=160万円
相続税総額:160万円×3人=480万円
B.生命保険を使った場合:
法定相続人1人当たり課税遺産総額:900万円
1人当たり相続税額:900万円×10%=90万円
相続税総額:90万円×3人=270万円(Aの場合の56%)
生命保険を使うと、210万円(Aの場合の44%)の節税となります。
まとめ
本記事では、生命保険を利用した相続税の節税方法を紹介しました。被相続人が被保険者となる生命保険は、死亡保険金から「500万円×法定相続人の数」が控除されます。仮に保険料が保険金と同等であっても、生命保険非課税枠相当分には課税されないので、節税効果があります。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
























