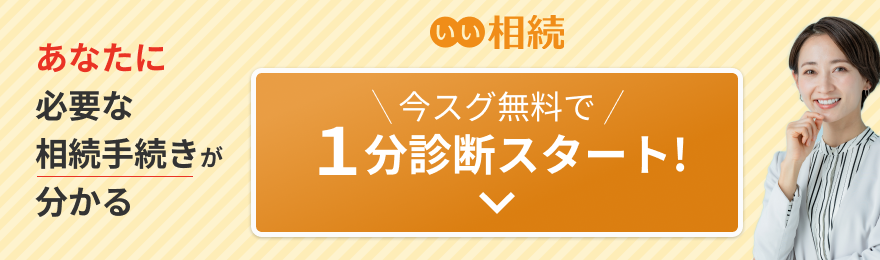相続のときに使える法定相続情報一覧図。どこで作ってもらえるの? いくらかかる?
配信日: 2023.01.14
本記事では、法定相続情報一覧図の概要をはじめ、どのように作成するのか、どこでもらえるのか、いくらかかるのかなどについて解説します。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
法定相続情報一覧図について知ろう
法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と相続人の関係を家系図のように記載したもので、法務局で認証を受けた書類のこと。亡くなった人と相続人との関係を公的に証明できるもので、法務局の法定相続情報証明制度に基づいて発行されるものです。
この制度は平成29年5月から始まりました。法定相続情報一覧図があることで、亡くなった人と相続人との関係を簡単に証明できるため、不動産登記手続きや金融機関手続き、相続税申告手続きなど、さまざまな手続きをスムーズに進めることが可能です。
一覧図がなければ、相続手続きなどの際に毎回、戸籍謄本や改製原戸籍謄本、除籍謄本といった書類の取得をしなければなりません。 これは時間や手間がかかるだけでなく、取得のための費用も必要なため、相続人の負担が大きくなりがちでした。しかし、一覧図があることでそれらの負担を軽減できます。
なお、法定相続情報一覧図は、法務局に依頼すれば作成してもらえるわけではない点に注意が必要です。一覧図を利用するためには、事前に自分で作成して法務局に提出し、認証を受けなくてはいけません。
作成のためにはまず、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、または戸籍の附票を取り寄せます。また、相続人全員の戸籍謄本や、申請者の氏名・住所を証明できる公的書類なども必要です。代理人に申請手続きを委任する場合は、委任状や代理人の資格を証明する書類を用意しましょう。
その後、被相続人の戸籍謄本から読み取った相続関係を、図形式か列挙形式のどちらかの書き方で記載します。記載する用紙は、A4サイズの白い紙を縦長にした状態で使用しましょう。
なお、記載方法の詳細については、法務局のホームページに詳細が説明されているため、参考にしてみてください。
作成した法定相続情報一覧図は、法務局に提出して一度認証を受ければ、5年間は無料で利用することが可能です。追加で必要になった場合も、費用を払わずに再交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の保管期間は5年間と決められており、保管期間を超えてしまった場合は、その一覧図を利用することはできないため、再度作成して法務局に認証の申し出をしなくてはいけません。その際は先述した書類を集めて、同じように作成する必要があります。
法定相続情報一覧図を作成しよう
法定相続情報一覧図は、一度作成して法務局の認証を受けてから利用できるのは5年間、という期間が設けられているものの、相続手続きをスムーズにするために重要な役割を果たします。
相続手続きに時間や手間をかけたくないと考えている人は、法定相続情報一覧図を作成するのも1つの方法です。作成する際は本記事で紹介した必要書類や手順を参考に、申請手続きをしてみてください。
出典
法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断