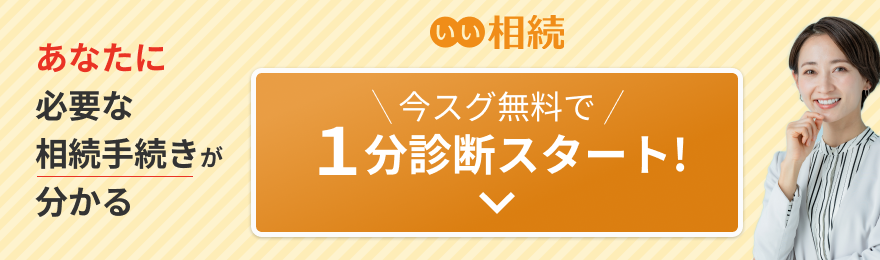今からでもできることや、やっていたほうが良いことはたくさんあるので、今回は今からできる相続対策を見ていきましょう。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
相続で問題となること
相続で問題となりやすいものは、お金に関わることです。特に問題となるのは、相続財産を「誰が」「どのように」受け取るのか、もしくは受け取らないのかということです。1つずつ見ていきましょう。
まずは、「誰が」相続人となるのか、確認する必要があります。
相続と聞くと、財産分与でもめるイメージがあるかと思いますが、負債や借金についても相続されるので、この点も注意が必要です。親戚の突然の死で借金を背負わされる、ということも相続では考えられます。また、行方不明や音信不通の親戚がいると相続手続きが進みません。相続人の対象となるのはどのような人たちなのかを把握するのはとても大切です。
次に「どのように」財産分与するのかでもめる場合があります。
現金を含む預貯金であれば分けやすいのですが、不動産や株式証券などになると分けるのが難しくなります。また、不動産の場合は登記が祖父母のままになっている場合もあり、相続手続きがスムーズにいかないこともあります。
相続人が誰になるのかを確認してみましょう
まずは、「誰が」相続人になるのかを確認してみましょう。
はじめに、相続人の対象となるのがどのような人なのかを確認しましょう。
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
1 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
2 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
【第1順位】被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡している ときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
【第2順位】被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の 父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているとき などは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
【第3順位】 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属) もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人 の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)
自分や配偶者の家族関係を把握していますか?親戚と疎遠になっていたり、行方不明になっていたりすると、相続手続きが進まないこともあります。まずは、第三順位の人までは把握できるように、家族と確認してみてください。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
事前に分けかたを決めておく、登記の名義を確認する
「どのように」で問題になりやすいのが、不動産などの分割しにくいものを相続することと、不動産の登記名義人が親に代わっていない場合です。
相続財産が不動産などの分割しにくいものだった場合
まず、相続財産が不動産などの分割しにくいものだった場合は、不動産をそのまま相続する、法定相続分より少なくなってしまう相続人に代償金を払う、不動産を売却して分ける、共有名義で相続する、といった方法があります。
相続手続きが始まってからどの分け方にするのかを考えると揉めてしまう原因になりやすいです。そこで、事前にどのように分けるのかを話し合っておきましょう。
登記の名義人が変わっていない場合
続いて、登記の名義人が親に代わっておらず、前の世代(例えば祖父母や曽祖父母)のままになっていると、前の世代の相続をやり直す必要があります。相続をやり直すということは、前の世代の相続人全員の印鑑届や実印、署名が必要になります。
こうなってしまうと、相続手続きがスムーズにいかず、さらに時間がかかってしまいます。面倒に感じてしまうかもしれませんが、いざ相続となってしまうと余計に面倒になって後回しになりがちです。
自分の代で登記がどうなっているかを確認することは、これからの世代のためにも今からやってみることをお勧めします。
登記の名義は最寄りの登記所で確認することができます。登記の名義が誰になっているかを確認しておきましょう。
「誰が」「どのように」をイメージしてみましょう
いかがだったでしょうか。相続は実際になってみないと手続きがわからなかったり、何から手を付けてよいかわからなかったりするものだと思います。そこで、事前に「誰が」「どのように」相続するのかをイメージしておきましょう。今からできることはたくさんあります。早すぎるということはないので、考えてみてください。
出典
国税庁 相続税のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部