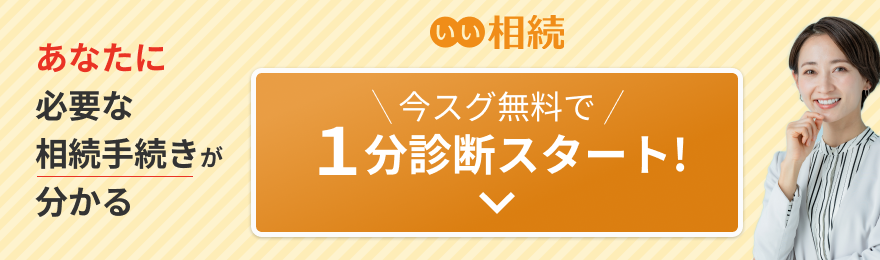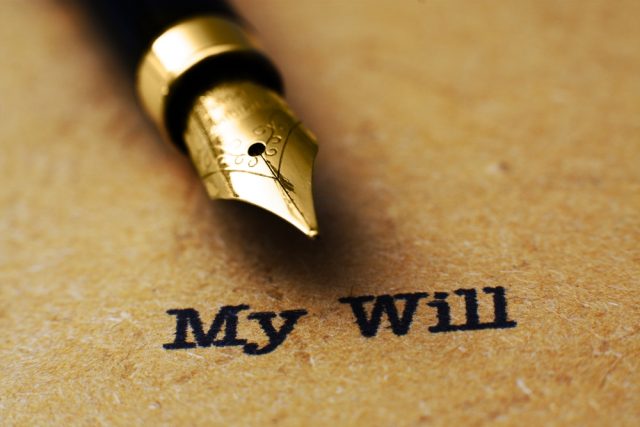
相続法は遺産相続の際に遺産の取り分を調整する制度で、遺留分は法定相続人が相続できる最低限の取り分のことです。
法改正でどのように変化があったのかを知り、いざという時に備えておきましょう。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
相続法改正と遺留分制度
2019年7月に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が施行されました。民法のうち相続法は40年近く改正されていませんでした。相続において遺留分とは「民法で定められた相続の権利がある人」である法定相続人が相続できる、最低限の取り分のことを指します。
遺留分に似た言葉に「法定相続分」があります。これは「民法で定められた法定相続人が相続できる遺産の割合」のことです。
なぜ改正されたのか?
戦前の日本では、戸主が家督相続をするため法定相続分や遺留分という考えはありませんでした。戦後、家制度が廃止され、子どものいる配偶者の3分の1の相続分が認められました。1980年には配偶者保護のため、子どものいる配偶者の相続分は2分の1まで引き上げられます。
その後、約40年ぶりとなる2018年7月に相続法が改正され、成立しました。この40年の間に大きく社会経済が変容し、改正前の相続法が時代と大きくずれた状態にあると明らかになったため、大幅に見直されました。
遺留分制度とは?
遺留分は、兄弟姉妹を除いた相続人が受け取れる相続財産の最低限の割合のことです。この遺留分を保障するのが遺留分制度です。相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、そのほかの場合は2分の1と定められています。
遺留分制度は、例えば遺言書に「長男に全財産を譲る」と書いてあった場合に効力を発揮。まず故人の意思を尊重して全財産は長男に引き継がれます。しかし、このままでは長男以外の法定相続人が相続を受けられなくなってしまいます。
そのため法定相続人は遺留分として一定割合の相続財産を得る権利が保障されているのです。
遺留分制度の変更点
2018年7月の相続法改正で、遺留分制度にも変更がありました。
1つ目は、遺留分を侵害された場合、相当額を金銭で請求できるという点。2つ目は、遺贈などを受けた者がその金銭をすぐ用意できない場合、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることも可能になる点です。この2点が変更されたことによりどのようなメリットがあるのか、詳しく説明します。
金銭で請求できるようになった
相続法の改正により、相続の際に遺留分を侵害された側は、遺留分侵害額に相当する金銭を遺贈や贈与を受けた者に対して請求可能になりました。旧制度で行使されていた遺留分減殺請求権は「現物返還」が原則で、金銭での支払いは例外的な位置付けでした。
遺留分減殺請求権が行使されると、例えば土地建物を相続した場合に複雑な共有関係が発生していました。法改正により金銭での支払いに一本化されたことで、複雑な共有状態からの回避が可能になりました。
支払期限の猶予を求めることができるようになった
相続法の改正により、遺留分侵害額が金銭で請求できるようになりました。これにより土地建物を相続し遺留分を請求されると、金銭を別に用意する必要が出てきます。
遺贈や贈与を受けた者がもし金銭をすぐ用意できない場合は、裁判所に対して金銭の全額もしくは一部の支払期限の猶予を請求できる制度も定められました。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
改正により遺言者の意思を尊重しやすくなった
相続法が改正される前は、例えば遺言者が土地建物を1人の人物に相続させたいと遺言を残しても、現物返還が原則であった遺留分制度により複雑な共有状態になる可能性がありました。
改正後は遺留分侵害額相当を金銭で請求できるため、共有状態を回避できます。相続法が改正され遺留分制度にも変更があったことで、目的の財産を受遺者に与えたいと考えている遺言者の意思を、より尊重できるようになりました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー