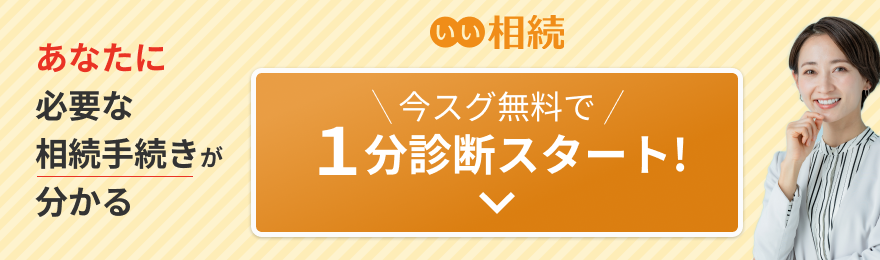遺留分侵害額請求の手続きはどのように行う? 期限はいつまで?
配信日: 2021.07.19

遺言などによりもらえる遺産が少なくなってしまった場合、遺留分侵害額請求の手続きを行うことで最低限もらえる遺産を請求できます。
この記事では、遺留分侵害額請求権とその手続き、請求の期限について解説します。記事を読み、遺産の配分に関する疑問を解決しましょう。

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
遺留分侵害額請求の基礎知識
遺留分侵害額請求とは、最低限相続できる遺産よりもらえた財産が少なかったとき、他の受遺者や生前に贈与を受けた受贈者に対して、遺留分を渡すよう請求することです。
ここからは、遺留分侵害額請求のもととなっている遺留分侵害額請求権、請求の対象となる財産、請求ができる人について解説します。遺留分侵害額請求を検討している人はぜひ最初にチェックしてください。
遺留分侵害額請求権とは?
配偶者、親、子供など法定相続人には、遺言の内容に関わらず相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。そのため、他の人が遺産を取りすぎてしまった場合には取り返す権利があるのです。
遺留分侵害額請求が必要なのは、最低限相続できる遺産、つまり遺留分を侵害されたときです。本来500万円遺産をもらえるはずの家族が100万円しか相続できなかった場合、400万円分の遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求権は配偶者、子ども、親のみ(兄弟姉妹以外の法定相続人)が持っている権利なので、生前の関係に関わらず行使が可能です。
遺留分侵害額請求ができる人
遺留分侵害額請求ができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。法定相続人に当たるのは、配偶者、子供、故人の親(子がいない場合)です。
法定相続人が配偶者のみの場合、遺留分は遺産の2分の1、直系尊属のみの場合は、遺留分の総額は遺産の3分の1です。また、配偶者と子供の場合は配偶者と子供(複数人要る場合はその中で均等に分ける)で4分の1ずつです。
そして、配偶者と故人の親の場合、配偶者の遺留分は3分の1、親は6分の1と決まっています。
請求ができるのは、遺留分を侵害された本人のみです。遺留分を早めに把握して手続きを進めましょう。
遺留分侵害額請求の手順
ここからは、以下のとおり遺留分侵害額請求の手続きの流れを解説します。
- 内容証明郵便を送る
- 任意で話し合いを行う
- 調停を申し立てる
- 訴訟を起こす
話し合いがスムーズに進めば、請求手続きが早く終わる可能性もあります。しかし、調停や訴訟が必要なこともあるので手続きの全体像を先に理解しておきましょう。
内容証明郵便を送る
侵害額の存在を知ったらまず最初に話し合い、それでも解決しない場合は内容証明郵便で通知書を送ります。内容証明郵便は、いつ、どんな文章を誰に送ったのか正式に記録が残る郵便です。
郵便局にも相談して、内容証明郵便を送りましょう。
任意で話し合いを行う
通知書の送付後、相手方と話し合いを行い、決着がつけば手続きは終了です。話し合いが進まない場合は、間に弁護士を入れて和解を目指しましょう。
調停を申し立てる
話し合いがうまく行かなかった場合、調停を申し立てることになります。調停では、裁判所が双方の意見を聞いて問題の解決に導いてくれます。
調停は裁判所に申し立てをしましょう。
訴訟を起こす
調停の申し立てでも問題が解決しない場合、訴訟となります。勝訴すれば、相手が支払いを拒んでいた場合でも強制的に遺留分を受け取ることが可能です。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には、期限があります。まず意識しておきたいのが時効。遺留分侵害額請求の時効は、遺留分の侵害を知ったときから1年です。そして、遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続発生から10年たつと請求ができなくなります。遺留分の存在を知ったらすぐに手続きを始めたほうがよいでしょう。
遺留分侵害額請求が不安なら専門家へ
遺留分侵害額請求権は誰でも持っている権利です。遺留分侵害額請求に関して少しでも不安があれば専門家に相談するのがよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー